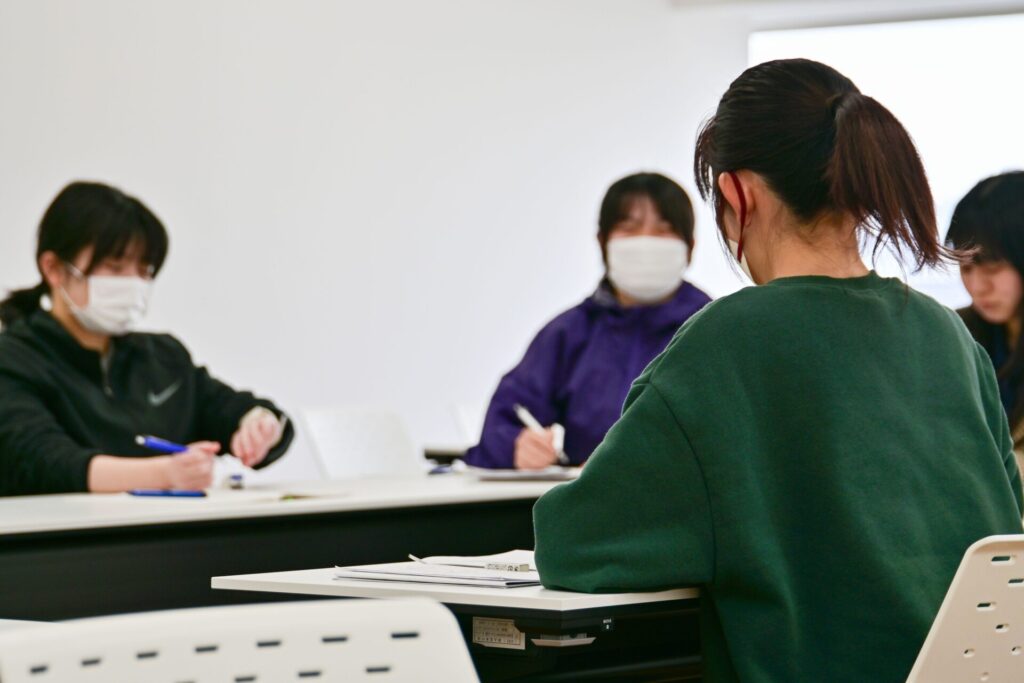3月13日、面接サクセス講座でおなじみの天野淑子先生によるグループディスカッション対策講座が開催されました。

選考でグループディスカッションが課される場面は多く、「どう振る舞えばいいのか分からない」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。今回の講座では、基本的な心構えや進め方を学び、実際に模擬ディスカッションを行うことで、実践的な力を養いました。
ディスカッションでは「議論を活発にしよう」という姿勢を見られています。自分がたくさん発言することだけが大事なのではなく、他のメンバーの意見にしっかり耳を傾け、「それはいい考えですね。付け加えさせてください」といった賛同の言葉を交えることも重要です。また、場の空気を読み、うなずいたり、相槌を打ったりすることで、積極的に議論に関わっている姿勢を示すことができます。先生によると、「発言できなくても、姿勢で爪痕を残そう!」だそうです。

さらに、ディスカッションが終わった後には必ず振り返りを行い、「次回はこうしよう」と改善点を見つけることも大切です。
ディスカッションは、①テーマの理解 → ②意見の出し合い → ③結論のまとめという流れで進みます。その中で、役割を意識して動くことがポイントになります。例えば、リーダー・司会役はメンバー全員の意見を引き出し、議論を円滑に進める役割を担います。タイムキーパーは制限時間内に話がまとまるよう管理し、話が脱線しないようサポートします。
今回の講座では、実際に模擬グループディスカッションを行いました。テーマは松山市の過去の試験で出題されたものから選ばれ、
- 「保健所で犬や猫の引き取り数を減らすために松山市は何をすべきか」
- 「愛媛FCの試合観戦を楽しむ人を増やすために松山市は何をすべきか」
という二つの課題について議論しました。
最初のディスカッションでは、全体的に発言が少なく、場の雰囲気も固かった印象でした。様子を伺う時間が長く、自己紹介をしてから始めれば、もう少しスムーズに進められたかもしれません。しかし、回を重ねるごとに意見が活発になり、議論も深まっていきました。
先生のフィードバックでは、「テーマを正しく理解することが大切」というアドバイスがありました。例えば、2つ目のテーマについて、「観戦者を増やす方法」ではなく、「試合観戦を楽しむ人を増やす方法」を考えることが重要だという指摘がありました。また、結論を無理にまとめようとするのではなく、審査員が見ているのは「どのような役割を担い、どのような発言をしたか」という点だそうです。
今回の講座を通じて、グループディスカッションでは「議論に貢献する姿勢」が評価されることを実感しました。積極的に話し合いに参加し、他者の意見を尊重しながら議論を深めていくことが大切です。
新年度は5月にグループディスカッション講座が開催される予定です。模擬ディスカッションで力をつけましょう!